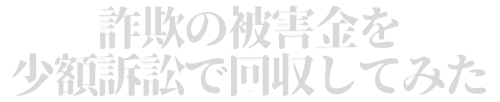はじめてでもわかる少額訴訟手続きの進め方
60万円以下の金銭トラブルを、スピーディかつ簡単な手続きで解決できるのが「少額訴訟制度」です。ここでは、実際に少額訴訟を起こす際の一連の流れを、ステップごとに分かりやすく解説します。
まずは少額訴訟が使えるか確認
金額と内容に条件あり
少額訴訟が利用できるのは、「60万円以下の金銭の支払い」を求める場合に限られます。また、物の引き渡しや損害賠償でも、請求が金銭であり上限額内であれば対象になります。
年に10回までしか提訴できない
原告1人あたり年間10件までという制限もあるため、複数件の訴訟を検討している場合は注意が必要です。
簡易裁判所に訴状を提出
相手の住所地を管轄する裁判所へ
訴訟は相手(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。たとえば相手が東京に住んでいる場合、東京の簡易裁判所に提出します。
訴状には証拠を添付
訴状には、請求の根拠となる証拠(契約書、振込明細、メールのやりとりなど)を添付しましょう。フォーマットは裁判所で配布しているほか、各地の裁判所のサイトでもダウンロード可能です。
裁判所から呼出状が届く
提出後1~2週間で期日が決まる
訴状を提出すると、裁判所が内容を確認し、双方に「口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状」を送付します。通常、提出から1~2週間で裁判期日が決まります。ただし、東京簡裁のように、扱う件数が多い場合は、訴状の提出から裁判期日まで時間がかかる可能性があります。
相手が来ない場合は?
被告が期日に出廷しなかった場合は、原告の主張が認められる判決が下されます(欠席判決)。

口頭弁論当日
準備しておくべきこと
・証拠書類の原本
・相手とのやりとりを時系列で整理したメモ
・質問されたときの受け答えのシミュレーション
これらをしっかり準備して臨みましょう。
時間は10〜30分程度
少額訴訟は、1回の期日で判決が下され、時間も10〜30分程度で終了することがほとんどです。
判決とその後の対応
その場で判決が言い渡される
裁判官は審理終了後、即日で判決を言い渡し、その内容が記載された「判決正本」は後日送付されます。
相手が支払わない場合は強制執行も
残念ながら、少額訴訟の判決が出ても、被告が支払いに応じない場合が少なくありません。その場合は「強制執行」の手続きに移ることになります。被告の銀行口座や給与の振り込み口座などを把握しておき、差し押さえをかけます。
じつは少額訴訟の勝訴判決を得ることよりも、差し押さえ、強制執行のほうが難易度が高いです。
まとめ
少額訴訟は、専門知識がなくても比較的スムーズに進められる制度です。「泣き寝入りするしかない」とあきらめる前に、一度制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。