少額訴訟の特徴とメリット
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを解決するために設けられた簡易な裁判制度です。原則として1回の期日で審理を終え、即日に判決が言い渡されるのが大きな特徴です。手続きがスピーディーで、本人訴訟(弁護士に依頼せずに自分で裁判を行う)も可能なため、日常的な金銭トラブルの解決手段として多く利用されています。
しかし、少額訴訟には一つ注意すべき点があります。それは、「被告(訴えられた側)が通常訴訟への移行を求めることができる」という点です。せっかく簡易な方法で進めようとしても、相手の判断によっては通常の裁判に切り替わってしまうことがあります。
被告側には通常訴訟への移行を求める権利がある
民事訴訟法第368条では、被告が第1回口頭弁論期日の前日までに「通常訴訟への移行」を申し立てることができると定められています。これは、少額訴訟が原告(訴える側)の希望によって申し立てられるのに対し、被告がそれを拒否する権利を持っているということです。
そのため、原告として少額訴訟を提起しても、被告が通常訴訟を望めば、その手続きはそちらに移行することになります。少額訴訟はあくまでも「相手が応じる場合」にのみ成立する制度だと理解しておく必要があります。

被告が通常訴訟への移行を求める理由とは?
被告が通常訴訟への移行を申し立てる理由はさまざまです。
- 少額訴訟では短時間で判決が出るため、十分な反論や証拠提出の時間がないと感じる
- 法律的な複雑な主張や、第三者の証言などを求めたい
- 弁護士に依頼して、正式な形で対応したいと考えている
- 少額訴訟の手続きに不安があり、より一般的な訴訟手続きを望む
このように、少額訴訟は簡易な手続きだからこそ、相手にとって不都合と感じられるケースもあります。
少額訴訟と通常訴訟に移行した場合の違いとは
通常訴訟に移行すると、以下のような点が変わってきます。
- 複数回の期日が必要となり、判決までに数ヶ月以上かかることもある
- 証拠の提出や証人尋問が行われるなど、手続きが本格化する
- 裁判所への出廷回数も増え、交通費や時間の負担も生じやすくなる
また、訴訟の進行に合わせて書面での主張(準備書面)や証拠説明書の作成が求められることもあり、法的知識がないまま対応するのが難しいと感じることもあるでしょう。
通常訴訟に移行されても焦らず対応するためのポイント
相手が通常訴訟を求めたからといって、焦る必要はありません。以下の点に注意して冷静に対応しましょう。
- 証拠資料(契約書・メール・領収書など)を整理し、主張の根拠を明確にする
- 法的な不安がある場合は、弁護士や司法書士に早めに相談する
- 本人訴訟でも、簡易裁判所の職員が手続きの説明をしてくれるため、心配しすぎないことも大切
実際、簡易裁判所では本人訴訟も多く、裁判所側もある程度は配慮した進行をしてくれることが多いです。
少額訴訟の限界とリスクも理解を
少額訴訟は非常に便利な制度である反面、相手方の意向次第で通常訴訟に変わるという「不確定要素」を持っています。特に相手が企業や代理人付きで対応してくる場合は、通常訴訟に持ち込まれるケースも珍しくありません。
そのため、少額訴訟を検討する際には、相手が応じない可能性も踏まえた上で、どこまで対応できるかを事前に想定しておくことが重要です。いざという時に備え、証拠の準備や専門家への相談など、柔軟な対応を心がけましょう。
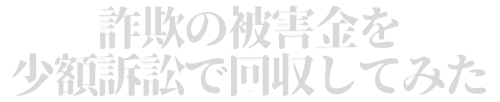
コメント