はじめに:少額訴訟で勝訴しても、すぐには終わらなかった
詐欺の被害金を回収するまでに私が最も苦心したのは、少額訴訟で勝訴することではありませんでした。それは差し押さえと強制執行です。
少額訴訟は相手の欠席裁判により全面勝訴することができました。勝負はここからだったのです。判決は相手に送達(届いて)して2週間で効力を生じます。ところが相手が住所地から転居していたため、判決が送達しなかったのです。
少額訴訟で勝訴したというのに、判決は「効力を生じない」ままでした。
判決送達のための調査と公示送達の申立
私は少額訴訟を起こしたときにも、付郵便送達を裁判所に申し立てました。このときは、相手が少額訴訟の訴状を受け取らなかったのです。
ちなみに付郵便送達とは、相手が訴状を受け取らなくても、訴状が郵送された時点で「送達」したとみなす制度です。付郵便送達が設けられているのは、訴状が被告に送達しない限り、裁判が始まらないからです。こうした制度がなければ、被告が訴状の受け取りを拒否し続ける限り、裁判を始められないことになります。
私は少額訴訟の判決が出た後で「公示送達」を申し立てました。
公示送達は、相手の住所がわからない場合でも、裁判所に判決が1週間掲示されることで、判決が「送達」したとみなす制度です。
公示送達の申し立て手続きは、付郵便送達と同じです。私は付郵便送達を申し立てたときと同じように、探偵事務所に相手の居住調査を依頼しました。この居住調査によって「相手が住所地に暮らしていない」ことを証明しなければならなかったのです。
居住調査の費用は約2万円でした。少額訴訟を提訴する際の付郵便送達と、判決が出た後の公示送達の2回で計4万円です。少額訴訟の提訴から差し押さえまで一連のプロセスで、この居住調査に最もお金がかかりました。
「判決の送達」が完了するまでに、少額訴訟から1か月を費やしました。思えば相手は少額訴訟の訴状も受け取ることなく、裁判にも現れませんでした。
こうした一連の対応から、相手は少額訴訟の判決も受け取らないことは予想がつきましたが、いたずらに時間が過ぎていくことに気をもむしかありませんでした。
ともかく、公示送達が完了したことで、ようやく少額訴訟の支払い命令付き判決を債務名義として、差し押さえと強制執行に移れるようになったのです。ただこの先に、さらなる難題が待ち構えていました。
差し押さえ申立書を送付…しかし3週間音沙汰なし
私は公示送達が終わると、すぐさま差し押さえ命令申立書を裁判所に郵送しました。
これで回収が進むと思いましたが、裁判所からは一向に連絡がありません。3週間が経過したところで、私は裁判所に電話をかけました。裁判所からの返答はこうでした。
「差し押さえ命令申立書に不備があったため、そのまま保留になってた」
私は思わず天を仰ぎました。
私が差し押さえようとしたのは「証券口座」でした。証券口座の差し押さえについてネットで調べてみても、見つかるのは銀行口座や給与の差し押さえの事例ばかりだったのです。証券口座の差し押さえは一般的ではなく、申立書の作成も簡単ではありませんでした。
SNSの投稿から証券口座の存在をつかむ
証券口座を差し押さえたのには理由がありました
私がお金を振り込んだ相手の銀行口座は、すでに差し押さえられていたのです。これでは私が差し押さえ命令を申し立てたところで、回収はほぼ不可能でした。
差し押さえ可能な資産は、証券口座ぐらいしかありませんでした。相手はSNSで株やFXの取引や、利用している証券会社の名前まで投稿していたのです。そのため、証券口座の特定は難しくありませんでした。
私はネットの断片的な情報をもとに、申立書をなんとか作成したのですが、その情報も正確ではなかったのです。

差し押さえ命令が競合…そして再申立へ
差し押さえ命令申立書に不備があったのは、私の自己責任です。それでも、こちらから裁判所に連絡していなければ、そのまま放置されていたに違いありません。裁判の原告(債権者)は、裁判所に進捗状況を確認することができます。不安があれば、裁判所に確認することをお勧めします。
ただ、こちらから確認の連絡をしてからの裁判所の対応は大変親切でした。そこから証券口座に対する差し押さえ命令申立書の再作成に向けて、一気に動き出したのです。裁判所と電話やFAXでやり取りしながら、法律書も教えてもらい、差し押さえ命令申立書を完成させることができました。何度も書き直しをして、差し押さえ命令申立書が受理されたときは、一人で喜びをかみしめました。
しかし、物事はそう簡単にはいきません。証券会社から届いた「陳述書」には、すでに他の債権者による差し押さえ命令が申し立てられていることが記されていたのです。
このように差し押さえが競合した場合、債権額に応じて按分されることになっています。私の債権額は30万円。按分には「供託」の手続きが必要になるうえ、按分額も数万円にとどまり、全額回収は不可能でした。
私は、いったん差し押さえ命令申立を取り下げ、別の証券口座に対して差し押さえ命令の申立をやり直すことにしました。再提出にまた時間がかかりましたが、今度は他の差し押さえ命令が競合することはなく、取り立てに進むことができたのです。
証券会社とのやり取りも一筋縄ではいかない
取り立てのため、私は証券会社に連絡しました。
ところが、証券会社のサイトを探しても、差し押さえの問い合わせ窓口などありません。お客様問い合わせ窓口に電話してみたものの、担当者は状況をまったく理解していない様子でした。
電話口からは「何の権限があって、取り立てようとしているのか?」という態度がひしひしと伝わってきます。弁護士ならともかく、一介の顧客(私もこの証券会社に口座を持っていました)から取り立ての連絡をされても、にわかに信じられなかったのも無理はありません。
そこで私は少額訴訟の事件番号や判決内容、相手の証券口座情報などを整理し、改めてメールで問い合わせました。
このメールがきっかけとなり、証券会社側も裁判所に確認したようでした。最終的に、私の取り立て依頼が正式なものであると認められ、ようやく手続きが進むことになったのです。
ついに振り込まれた回収金!そこに至るまでの3年間
少額訴訟の判決から半年。ようやく相手の証券口座からの取り立てることができました。私の口座にお金が振り込まれました。
思えば被害に遭ってから(相手から返済を拒否されてから)3年が過ぎていました。自分で少額訴訟を起こして、訴状や差し押さえ命令申立書などの書類を自力で作成。裁判所と何度もやりとりし、証券会社にも電話とメールで説明…思えば長い道のりでした。
振り込まれた金額は、判決の支払い命令の全額でした。私は一人で喜びをかみしめました。
まとめ:情報と粘り強さが回収の鍵
少額訴訟で勝訴することは、あくまでもスタートラインです。
お金を回収するには、差し押さえと強制執行を進めなければなりません。判決の公示送達、差し押さえ命令申立書の作成など、法律の素人には簡単ではありませんでした。
それでも、付郵便送達と公示送達の住居調査を除けば、自力で少額訴訟と差し押さえを実行できました。差し押さえ命令申立書の作成には、裁判所の手助けを借りることになりましたが、法律の専門家でなくても、お金を回収できました。
詐欺被害にあっても、自力での少額訴訟と差し押さえの可能性が残されているのです。
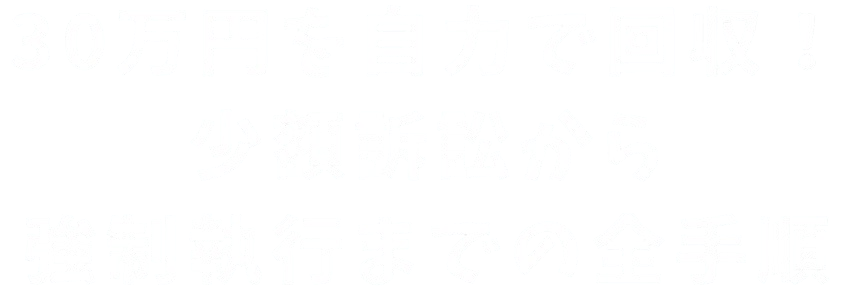



コメント