少額訴訟の「付郵便送達」申し立てと流れは?
訴状が相手に届かないと裁判は開かれない
少額訴訟を起こしても、相手に訴状が「送達」されなければ、裁判が始まることはありません。
じつは少額訴訟などの裁判を起こされた被告の中には、意図的に訴状の受け取りを拒否したり、居留守を使ったりする人もいるのです。実際に筆者の少額訴訟でも相手が訴状を受け取りませんでした。
相手に訴状の受け取りを強制することはほぼ不可能です。いたずらに時間だけが過ぎてゆき、焦りが募りました。
ただ、訴状を受け取らない相手に対しても裁判を進めるための制度が用意されています。それが「付郵便送達」という制度です。一般にはあまり聞き慣れない付郵便送達ですが(筆者も少額訴訟を起こすまでは知りませんでした)、訴状の受け取り拒否にあった際に非常に重要な制度です。
送達の基本ルールとは?
少額訴訟を起こすと、簡易裁判所から訴状が書留で被告に郵送されます。そして被告が訴状を受け取ることで「送達」が成立します。これを「特別送達」といいます。
原告が少額訴訟の訴状を簡易裁判所に提出するだけで裁判が開かれるわけではなく、被告に訴状が送達していることが前提です。訴状が送達しなければ、被告は自身が裁判を起こされていることを知りえないからです。
つまり、次のようなケースでは訴状は「送達」しないことになります。
- 郵便局から「不在」のまま戻ってきた
- 「受け取り拒否」で返送された
- 「転居先不明」として返送された

被告が訴状を受け取らないときの「付郵便送達」とは?
相手が訴状を受け取らない場合に、原告は「付郵便送達」の利用を裁判所に申し立てることができます。付郵便送達の申し立てが認められると、裁判所が訴状を相手の住所に「郵送した」ことをもって、実際に相手が受け取らなくても送達が成立したとみなされます。
つまり付郵便送達によって、少額訴訟の訴状が相手に届かなくても、裁判を始めることが可能になります。ただ付郵便送達の申し立てには、相手の住居調査や住民票の取得などが必要です。
付郵便送達の手続きの流れと必要書類
付郵便送達を申し立てるには、以下のような手続きを行います。
付郵便送達申立ての手順
- 裁判所に「付郵便送達申立書」を提出(決まった書式はありません)
- 被告の住所が正しいことが分かる資料を添付(住民票など)
- 被告の居住実態がわかる居住調査報告書を添付
以下は裁判所公式サイトの記載例を参考にした、付郵便送達の申立書です。
付郵便送達申立書の記載例
○○簡易裁判所 御中
令和◯年 (少コ)第〇号 〇〇〇〇事件(注:事件番号と事件名を記入)
原告 〇〇〇〇(住所:〇〇市〇〇町〇番地) 印
付郵便送達申立書
上記事件につき、被告に対しては、訴状記載の住居所あてて付郵便による送達をされたく申し立ていたします。
記
添付書類
□ 調査報告書
□ 住民票
□
以上
付郵便送達で少額訴訟はどう進む?被告が出廷しなかったら?
少額訴訟の訴状が、被告の受け取り拒否によって返送されてきた場合、簡易裁判所から原告に、付郵便送達の申し立てをするか、訴えを取り下げるかといった対応について、裁判所から事前に確認の連絡があります。
付郵便送達には住居調査が必要
少額訴訟を続ける場合は、付郵便送達申立書に、相手の居住調査結果や住民票を添えて裁判所に提出します。申立書は郵送でかまいません。
ただ、付郵便送達の申し立てる際には、相手が実際に住んでいない住所を使うなど、虚偽の申し立ては許されません。相手が住所地に暮らしていながら訴状を受け取らないことを、原告が調べて、裁判所に報告書を提出する必要があります。この報告書は、先にご紹介した付郵便送達の申立書に添付します。
付郵便送達の住居調査は「建物外観の写真」「電気・ガス・水道メーターの作動状況」「郵便受けの様子」「近隣住民への聞き込み」などが必要です。
以下は裁判所公式サイトの記載例を参考にした、住居調査の報告書です。報告書にも決まった形式はありませんが、次のような調査項目を記入する必要があります。
付郵便送達・住居調査報告書の記載例
(別紙)
調査報告書
下記のとおり、訴状記載の住居所について調査した結果、被告が居住していることを確認しました。なお、被告の就業場所等他に送達すべき場所は不明です。
記
調査者 氏名
調査の日時 令和 年 月 日午前・午後 時 分 頃
調査の場所 住所
建物の外観 ビル・集合住宅・一戸建
表札の有無 あり・なし
電気メーター 動いている(微動・勢いよく動いている ・停止している)
生活感 あり・なし
郵便物 たまっている(不在の様子)・たまっていない(回収されている様子)
呼び鈴に対する応答 あり・なし
応答者 氏名
近隣への聞き込み結果
対象者の氏名
聴取内容
以上
こうした住居調査は自力でもできないことはありませんが、プライバシーの観点や相手がオートロックのマンションに暮らしている場合などは、簡単ではありません。とくに相手が遠方に暮らしている場合は、時間と手間、現地までの交通費がかかります。
付郵便送達の住居調査を手掛けている探偵事務所も多く、費用は2万円から10万円ほどです。地域にもよりますが、筆者が住居調査を依頼した探偵事務所は約2万円でした。
住民票を取得するには
付郵便送達の申し立てには、住居調査とともに住民票などの取得が必要です。住民票の取得は、原告が役所に取得方法や費用を確認して、自分自身で申請しなければなりません。
たとえば東京都大田区では、住民票の写しの取得費用は300円となっており、定額小為替(郵便局で購入可)を申請書に同封します(オンライン決済可能な役場もあります)。申請書には申請者(原告)の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)や訴状のコピーを同封します。
住民票の写しの申請方法や費用は役所によって異なっており、ホームページなどで確認が必要です。
もし仮に少額訴訟の訴状を受け取らなかった被告が、少額訴訟の裁判も欠席した場合はどうなるでしょうか?裁判所は原告の主張内容や証拠をもとに判断を下し、被告欠席のまま判決が言い渡されることになります(欠席裁判)。
注意点とよくある質問
Q:相手の住所が不明な場合はどうなる?
→相手の住所が不明なままでは付郵便送達を申し立てることはおろか、少額訴訟を起こすことができません。少額訴訟を起こすにあたっては、相手の正確な現住所を把握しておく必要があります。この場合の「住所」とは、住民票の住所である必要はなく、相手が居住している場所をさします。業者に住所調査を依頼することもできますが、それなりの費用がかかります。
Q:相手が引っ越していたら?
→新しい住所がわかっていれば再送達の申し立てが必要です。もとの住民票の所在地で、住民票の取得などを図ることになります。仮に被告が住所地に住んでいるかどうかわからない場合や、転居先が不明の場合は、被告が訴状を受け取ることができないため、少額訴訟を起こすことはできません。裁判での解決を図ろうとすれば、少額訴訟の訴えを取り下げて、通常訴訟での提訴を検討することになります。
Q:送達が成立するのはいつ?
→裁判所が訴状を郵送した日が「送達日」として扱われます。
送達されないまま諦めずに、付郵便送達の活用を
被告が訴状を受け取らないことは、少額訴訟の原告にとって大変悩ましい問題です。原告自身の力で訴状を受け取らせることはできないため、時間ばかりがすぎていくことに焦りが募ります。ただし、このような場合に「付郵便送達」を申し立てることで、少額訴訟を開始できる可能性が広がります。
少額訴訟は審理が1回ですむ簡易な裁判で、訴状の作成もそれほど難しくはありません。それでも、相手に訴状を受け取らせることがじつは重要な第一歩になりうるのです。
筆者にとっても、付郵便送達の申し立てが少額訴訟の最初の山場でした。相手は付郵便送達が認められた後に、住所地から転居したためです。あと一歩遅ければ、住所不明で、少額訴訟を提訴することもできなくなるところでした。
少額訴訟での解決を望む場合、相手の動向と対応の迅速さが大きなカギを握ることになります。
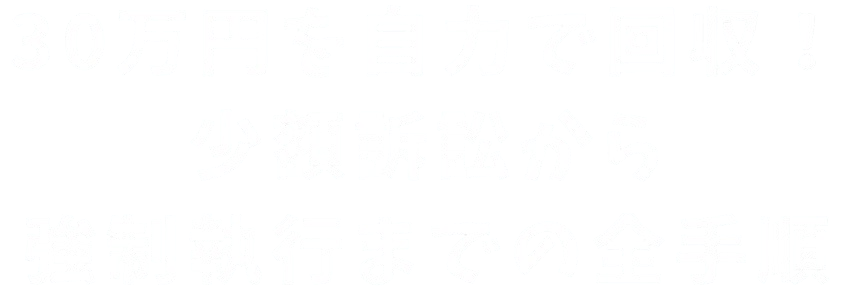



コメント