少額訴訟で勝訴しただけでは、お金は戻ってこない
少額訴訟で勝訴して、支払い命令付きの判決が出たとしても、それだけで自動的にお金が戻ってくるわけではありません。
少額訴訟で勝訴しても、喜ぶのはまだ先です。被告が判決に従って、お金を払うとは限らないからです。裁判所は支払い命令付きの判決(債務名義)を出すだけで、被告に支払いを強制してはくれません。少額訴訟の支払い命令判決は「裁判所から支払い命令という法的根拠を与えられた」だけなのです。
もしも被告が支払い命令付きの判決に従わなかった場合、判決内容を実現する=強制執行するのは、裁判所ではなく債権者(原告)自身です。
少額訴訟の相手が判決に従わない場合を想定して、原告は少額訴訟の提訴とともに、差し押さえの準備まで進めるべきでしょう。少額訴訟の相手がお金の回収を恐れて、資産隠しをしたり、行方をくらましたりするリスクがあるからです。
強制執行とは?支払い命令を実行に移す方法
相手が少額訴訟の判決に従わなかった場合に、債権者(原告)は「差し押さえ命令」と「強制執行」を裁判所に申し立てることです。
差し押さえ可能な財産には、次のようなものがあります:
- 預金
- 給与
- 動産・不動産
- 売掛金などの債権
このうち動産や不動産を差し押さえるには「競売」の手続きが必要になります。裁判所に競売を申し立てて、動産や不動産を現金化しなければなりません。こうした手間やコストを考えると、少額訴訟では預金や給与を差し押さえることが現実的な手段になります。
差し押さえに必要な情報とは?
少額訴訟の判決を債務名義として差し押さえと強制執行を申し立てるには、債権者(原告)自身が回収可能な相手の資産を把握しておく必要があります。
たとえば相手の預金口座を差し押さえる場合にも、債権者が金融機関名と支店名を特定しておく必要があります。どの銀行のどの支店に相手の口座があるかがわからないと、差し押さえ・強制執行はできません。
また、給与を差し押さえる場合にも、相手の勤務先・所在地を把握しておかなければなりません。相手の口座や勤務先がわからなければ、少額訴訟で勝訴しても、差し押さえは難しくなります。
差し押さえの現実:こんな困難が
差し押さえで難しいのは次のようなケースです。
- 相手の口座情報がわからない
- 口座に資産が残っていなかった
- 勤務先をすでに辞めていた
- 名義を変更されていた
少額訴訟で支払い命令付き判決を得ても、差し押さえる財産が見つからなければ、回収は困難です。回収の見込みがない場合は、差し押さえ命令を取り下げることになります。

差し押さえ成功のためにできる準備
回収成功の鍵は、差し押さえ可能な相手の資産を把握しておくことです。
もっとも有力なのは、お金を振り込んだ相手の銀行口座です。ただし、少額訴訟を起こされた相手も警戒を強めるはずです。銀行口座を解約したり、他の口座にお金を移したりするリスクも考えられます。
相手のホームページやSNS、メールなどに口座情報がないか、もう一度確認しましょう。相手が勤め人なら、給与のほかにも、勤務先の取引銀行や支店に口座があるかもしれません。
どうしてもわからなければ、探偵事務所に資産調査を依頼する選択肢もあります。ただ、遺産調査にはそれなりの費用が必要です。
弁護士を「受任(訴訟代理人を依頼)」していた場合は、弁護士会を通じた金融機関への照会が可能です。ただし少額訴訟では、弁護士に受任すると「費用倒れ(赤字)」になる可能性があります。費用対効果を考えるとあまり現実的な手段とはいえません。
「財産開示手続き」と「第三者からの情報取得手続き」
なお、少額訴訟判決などの債務名義がある場合には、「財産開示手続き」「第三者からの情報取得手続き」を裁判所に申し立てることができます。
財産開示手続の申し立てが認められた場合、債務者(被告)は指定された期日に裁判所に出頭し、資産状況について陳述(報告)しなければなりません。一方、第三者からの情報取得手続きは、第三者(金融機関や被告の勤務先)に対して、不動産・預貯金・給与・株式や証券などの資産状況を債権者に提供させる制度です。
仮に財産開示手続を債務者が無視した場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される可能性があり、従来よりも罰則が強化されました。もし相手の資産状況がどうしても特定できなければ、財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きを試してみる価値はありそうです。ただ両方とも裁判所への申し立てが必要であるなど、手続きは簡単ではありません。
差し押さえ・強制執行の費用と手続き
差し押さえと強制執行には以下のような費用がかかります(裁判所の公式サイトを参照):
- 収入印紙代(申立手数料):4000円
- 予納郵券代(切手代):(例)東京地方裁判所裁判所は計4000円(裁判所によって異なる)
また、手続きには以下のようなステップが必要です:
- 債務名義(判決)を取得
- 差押命令申立書を作成
- 裁判所へ提出
- 相手の口座や給与を差し押さえ、自身で金融機関などに対して取り立てを行う
差し押さえ命令の申し立てから取り立てまでは、おおよそ1〜2か月程度かかります。筆者の場合は差し押さえ命令の申し立てから3か月ほどをかけて、取り立てを実現することができました。少額訴訟の提訴から数えると、回収に8か月近くを費やしたことになります。
少額訴訟の裁判自体は、相手の欠席裁判によって数分で終わりました。ただ、相手が少額訴訟の訴状を受け取らなかったため期日が延期になりました。さらに付郵便送達の申し立て手続きにも時間をとられました。
また差し押さえ命令を申し立てる際にも、やはり相手が判決を受け取らなかったことと、何度も差し押さえ命令申立書を書き直さなければならかったことが、時間のロスにつながりました。
少額訴訟や差し押さえを管轄する裁判所の規模が大きいほど、手続きにかかる時間が長引く傾向があります。少額訴訟や差し押さえの手続きは、相手の住所地を管轄する簡易裁判所になるため、いかんともしがたい点があります。ただ時間がかかるほど、回収も難しくなってしまうため、債権者(原告)としては事前の準備がより大切になります。
年金は差し押さえできる?
なお、年金は原則として差し押さえが禁止されています(民事執行法152条など)。ただし、年金として口座に振り込まれた後に、生活費などとして残っているお金は、差し押さえが認められる場合もあります。
とはいえ、実務上は「年金受給者からの回収」は簡単ではありません。
このように、少額訴訟で支払い命令付き判決を得ても、差し押さえと強制執行には手間とコストがかかります。相手に回収可能な財産がない、または不明である場合、判決を得ても実際の回収ができないケースも珍しくありません。そのため差し押さえと回収を念頭に置きながら、少額訴訟を進める必要があります。
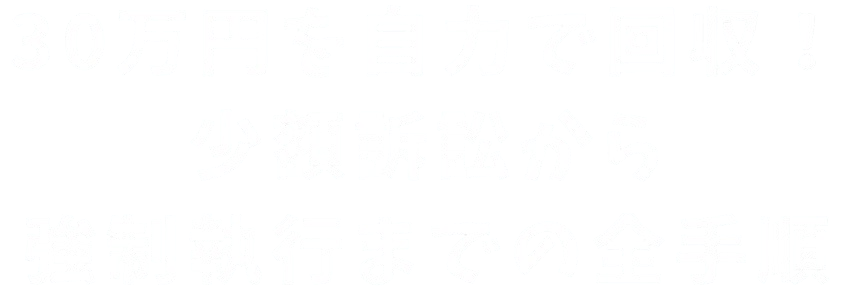

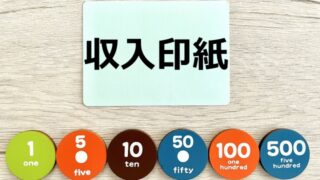
コメント