少額訴訟とは何か、なぜ費用が明確なのか
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、簡易・迅速な解決を目的とする裁判制度です。
少額訴訟は通常訴訟よりも手続きが簡素で、1回の審理で判決が出るのが特徴です。そのため、費用も収入印紙と予納郵券代の数千円から1万円前後で収まるケースが多く、通常訴訟に比べて、訴える側・訴えられる側双方にとって経済的負担が軽いのがメリットです。
ただ少額訴訟では原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所で開かれるため、相手が遠方に暮らしている場合は、簡易裁判所までの交通費がかかります。
さらに相手が少額訴訟の訴状を受け取らなかった場合に「付郵便送達」の申し立てが必要になると、相手の居住調査をしなければならないケースもあります。その場合、探偵事務所への調査依頼費や現地までの交通費などの出費を見込んだほうがいいでしょう(自力で住居調査が可能な場合や、相手の住所地が近隣である場合にはそれほど費用はかかりません)。
収入印紙代や予納郵券(切手)代が必要
少額訴訟にかかる費用をおおまかに計算します。
少額訴訟に最低限必要な費用は、収入印紙代(請求額によって1000円~6000円)と予納郵券代(6000円前後、裁判書類の郵送に使われる)です。少額訴訟では請求額の上限が60万円であるため、収入印紙代と予納郵券代を合わせても最大で1万2000円になります。
ただ少額訴訟を管轄する簡易裁判所が遠方である場合は、交通費(往復2万円として計算)も必要です。また相手が訴状を受け取らなかった場合は、先述した付郵便送達の居住調査費用(探偵事務所に2万円で依頼したと計算)、相手の住民票取得費用(1000円以内)が別途かかります。これらを合わせると5万円前後になります。
管轄の簡易裁判所が近くにあって交通費がそれほど必要ない場合や、相手が訴状を受け取った場合は、少額訴訟の費用は収入印紙代と予納郵券代の計1万2000円前後だけです。
このうち収入印紙代と予納郵券代は「訴訟費用」として、被告に請求することができます。ただし訴訟費用を請求するためには、少額訴訟の訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」という一文を記入しておく必要があります。とはいえ訴訟費用の請求には、簡易裁判所への申し立てが必要になるなど手間がかかるため、実際に請求する人は多くありません。
少額訴訟に必要な主な費用の内訳
a. 収入印紙代(訴訟手数料)
少額訴訟を提起する際に必要となる費用で、請求額によって異なります。収入印紙は郵便局などで購入することができ、訴状に貼付します。必要となる収入印紙代は、以下の通りです。
少額訴訟の収入印紙代
少額訴訟で必要となる収入印紙代は、以下のフォームから計算することができます(念のため裁判所でもご確認ください)。
請求金額から収入印紙代を自動計算
b. 郵便切手代(予納郵券)
予納郵券は裁判所が相手方に訴状などを送付するために使われます。予納郵券代は管轄の裁判所によって異なります。たとえば東京簡易裁判所では6,000円程度が必要で、切手の種類ごとに枚数が決まっています。
東京簡易裁判所の予納郵券代(令和6年9月現在)
切手が余った場合は、少額訴訟の原告に返還されます。逆に切手が足りなくなった場合は、不足分を請求されることがあり、簡易裁判所にあらためて郵送することになります。
切手代の値上がりによって予納郵券代も変動するため、詳細は少額訴訟を管轄する簡易裁判所のホームページでご確認ください。

c. 付郵便送達の居住調査
もし少額訴訟の相手が訴状を受け取らなかった場合、裁判はどうなるでしょうか?
被告が訴状を意図的に受け取らない場合、裁判を始めることができません。このような場合に、原告は先述した「付郵便送達」を簡易裁判所に申し立てることができます。
付郵便送達は少額訴訟の訴状が郵便局から発送されたことをもって、被告が訴状を受け取ったものとみなす制度です。この付郵便送達が設けられているのは、被告が訴状の受け取りを拒否する限り、裁判を回避し続けられるためです。
付郵便送達を申し立てるには、相手が住所地に暮らしているのに、居留守などを使って訴状を受け取らないことを、住居調査によって証明する必要があります。そのためには、相手の家・マンション・アパートの外観写真、電気・ガス・水道メーターの作動状況、郵便受けの様子、近隣住民への聞き込み、住民票の取得などが必要です。
原告自身で付郵便送達の住居調査をする場合は、現地までの交通費と住民票の取得費用ぐらいしかかかりません。とはいえ個人での住居調査は簡単ではありません。とくに相手が遠方に暮らしている場合は、交通費もかかります。住居調査を探偵事務所に依頼した場合は、数万円の費用が相場です。
弁護士や司法書士に依頼した場合の費用
少額訴訟は本人訴訟でも十分に対応可能です。実際に少額訴訟の9割以上が本人訴訟だといわれています。それでも不安がある場合には弁護士や司法書士に依頼して、少額訴訟に代理出席してもらうこともできます(裁判所が許可した家族や従業員の代理出席も可能です)。
弁護士に依頼した場合の費用は弁護士事務所によって異なりますが、以下が一般的です。
- 相談料:30分5000円~
- 着手金:5万円〜(着手金なしの弁護士事務所も)
- 成功報酬:訴訟額の10%〜30%
- 交通費:実費
- 日当:弁護士事務所による
少額訴訟では請求額(被告に支払いを求める金額)が60万円以下と、通常訴訟に比べるとそれほど多くありません。そのため、弁護士への相談料や着手金、成功報酬などの費用が回収額を上回り、場合によっては赤字になる恐れもあります。少額訴訟を弁護士に依頼する前に、費用対効果を慎重に考えなければなりません。
また弁護士事務所のほうでも、少額訴訟では報酬がそれほど見込めないため、訴訟代理人を引き受けてくれないケースもあります。さらに裁判所が、原告本人に「出頭命令」を出す可能性があります。その場合には弁護士に訴訟代理人を依頼していたとしても、原告本人が少額訴訟の裁判に出席しなければなりません。
ただ、訴状などの書類作成だけを司法書士などの専門家に依頼することもできます。費用は司法書士事務所によって異なりますが、おおむね5万円前後でしょう。
相手に費用を請求できるケースとは?
少額訴訟では、訴訟費用(収入印紙代や予納郵券代)は相手に負担を求めることができます。ただ訴訟費用の請求には裁判所への申し立てが必要になるため、手間と時間を考えると、実際に請求することはあまり現実的とはいえません。
一方、弁護士や司法書士などへの相談料や着手金、成功報酬などの費用は、特別な事情がない限り自己負担となります。
実際のケースでの少額訴訟費用シミュレーション
ケース1:請求金額10万円+自力で訴訟
- 収入印紙代:1,000円
- 郵便切手代:6,000円(東京簡易裁判所の例)
- 書類作成代:500円
合計:7,500円程度、別途簡易裁判所までの交通費
ケース2:請求金額50万円+弁護士に依頼
- 収入印紙代:5,000円
- 郵便切手代:6,000円(東京簡易裁判所の例)
- 弁護士費用:相談料2時間2万円+着手金5万円+成功報酬(20%で計算)10万円+交通費と日当2万円
合計:約20万1,000円程度(弁護士費用は事務所によって異なります)
少額訴訟はコストを抑えて迅速に紛争を解決できる有効な手段です。収入印紙や郵便切手代など、かかる費用は限られており、誰でも利用しやすいのが特徴です。
ただし、少額訴訟を弁護士や司法書士などの法律職に相談・依頼する場合や、付郵便送達の住居調査などで追加費用が発生することもあります。

少額訴訟の費用はシンプルで予測しやすい
少額訴訟はコストを抑えて迅速に紛争を解決できる有効な手段です。収入印紙や郵便切手代など、かかる費用は限られており、誰でも利用しやすいのが特徴です。少額訴訟を管轄する簡易裁判所が遠方でなければ、数千円の費用ですむ場合もあります。
ただし、付郵便送達の申し立てが必要になる場合や、相手の住所調査を依頼した場合、さらに弁護士や司法書士に相談した場合は、多額の費用が発生することもあります。回収する金額を考えれば割に合わない場合や、費用が回収額を上回る場合さえありえます。
なにより注意が必要なのは、少額訴訟に限らず、支払い命令付きの判決が出たとしても、相手がそれに応じない、あるいは相手に資産がない可能性があることです。前述したように、弁護士が少額訴訟をなかなか引き受けないのも、回収が見込めないリスクがあるためです。
相手が判決に従わない場合には、相手の資産を差し押さえ、強制執行する手続きといった費用が別にかかることになります。
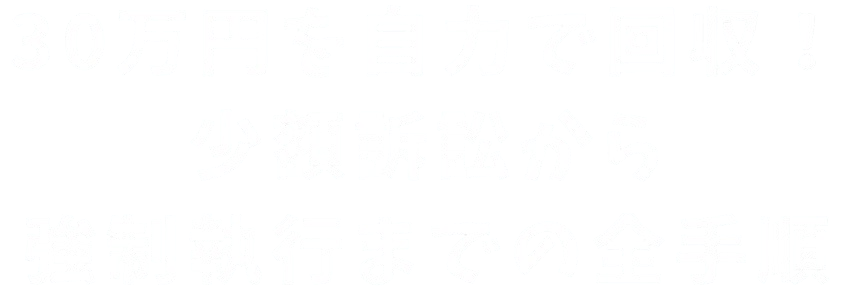



コメント